HOME / こんなとき…の手続き
家族を扶養にいれたい(被扶養者の認定)
短期給付(健康保険)は、組合員だけでなく、組合員に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいますが、被扶養者の範囲は法律で定められています。
組合員の家族が「被扶養者」の資格を得るためには、共済組合の『認定』を受ける必要があります。「税法上の被扶養者」「配偶者」などが無条件で認定されるわけではありません。(扶養の認定要件参照)
認定を受けられるのは、被扶養者の範囲に該当し、次の条件を満たしている人に限られます。
- 主として組合員の収入によって生活していること
- 年間収入が130万円(障害年金受給者または60歳以上である者は180万円)未満で、組合員の収入の2分の1未満であること
- 75歳未満。
【被扶養者の範囲】
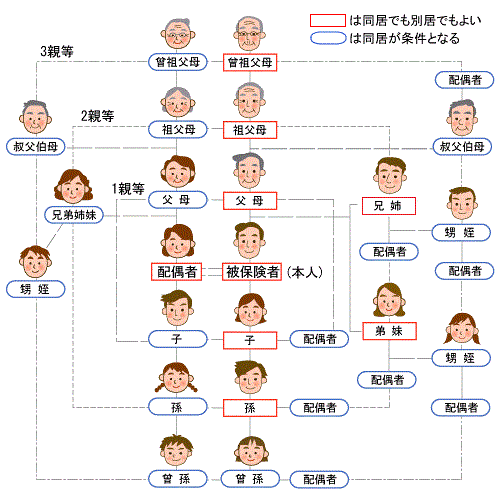
被扶養者になれない人・状況
- 共済組合の組合員または他の健康保険・船員保険の被保険者になっている人
- 組合員以外の人が、その家族について国などから扶養手当またはこれに相当する手当を受けているとき
- 組合員が他の人と共同して同一人を扶養する場合に、その組合員が主たる扶養者でないとき
- 年額130万円(月額108,334円)以上(障害年金受給者または60歳以上である者は180万円以上,配偶者を除く19歳以上23歳未満である者は150万円以上)の恒常的収入(※)がある人
- 18歳以上60歳未満のうち「学生」「身体障害者」「病気・けがなどにより就労能力を失っている人」に当てはまらない人
- 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者の人(75歳以上、または65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けている方)
※ 退職手当や相続による収入など『一時的な収入』は含まれません。
※ パートや非常勤講師など月々給与を受けている場合は、年間130万円を実際に超えた時、さかのぼり扶養からはずします。
また、年間130万円とは、どの時点からの12か月をとっても130万円を超えないことです。
≪被扶養者認定の手続きについて≫ | ||
被扶養者となるためには、共済組合の認定を受けなければなりません。 続柄別にご案内していますので、下記よりご確認ください。 |
||
| 扶養の認定を受ける方は? | ||
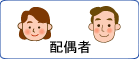 |
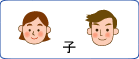 |
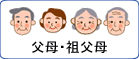 |
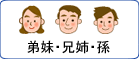 |
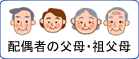 |
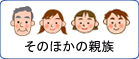 |
東京科学大学福利厚生給与課福利厚生第1グループ